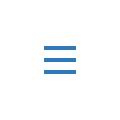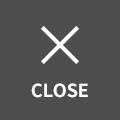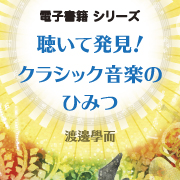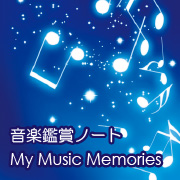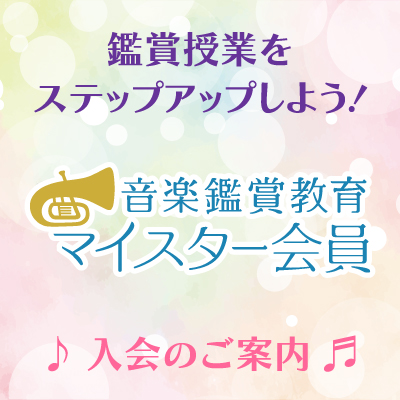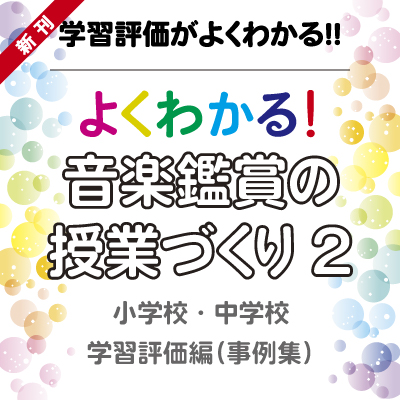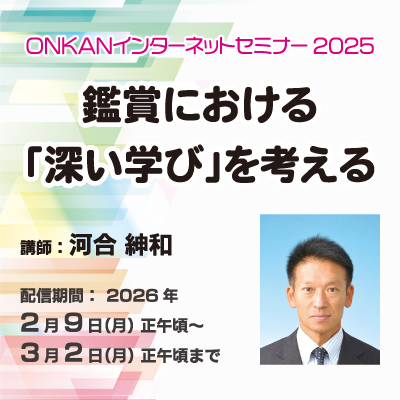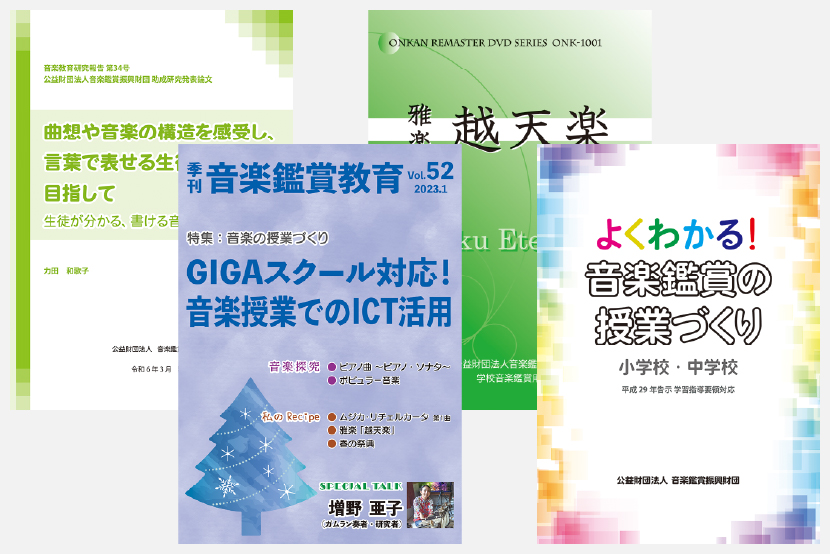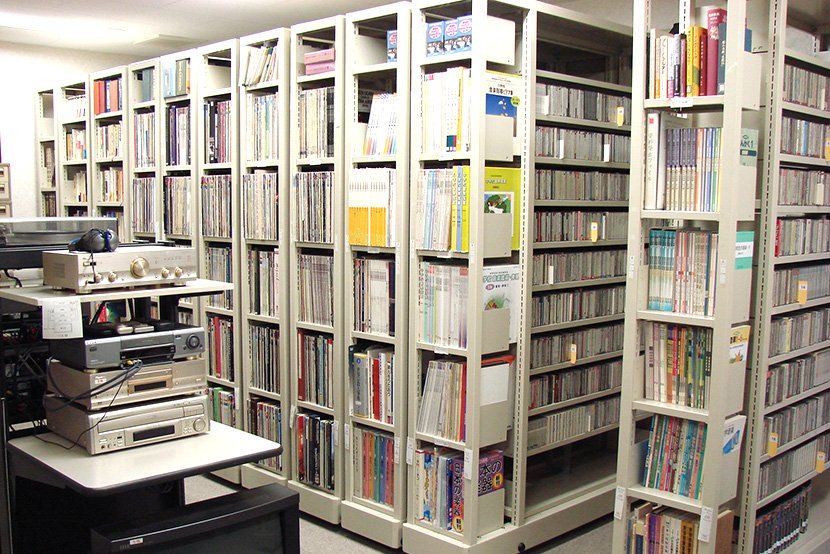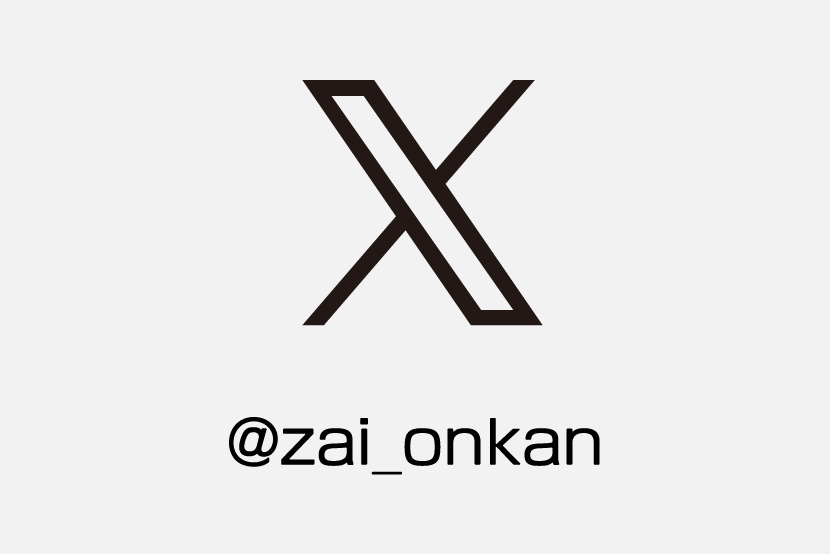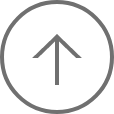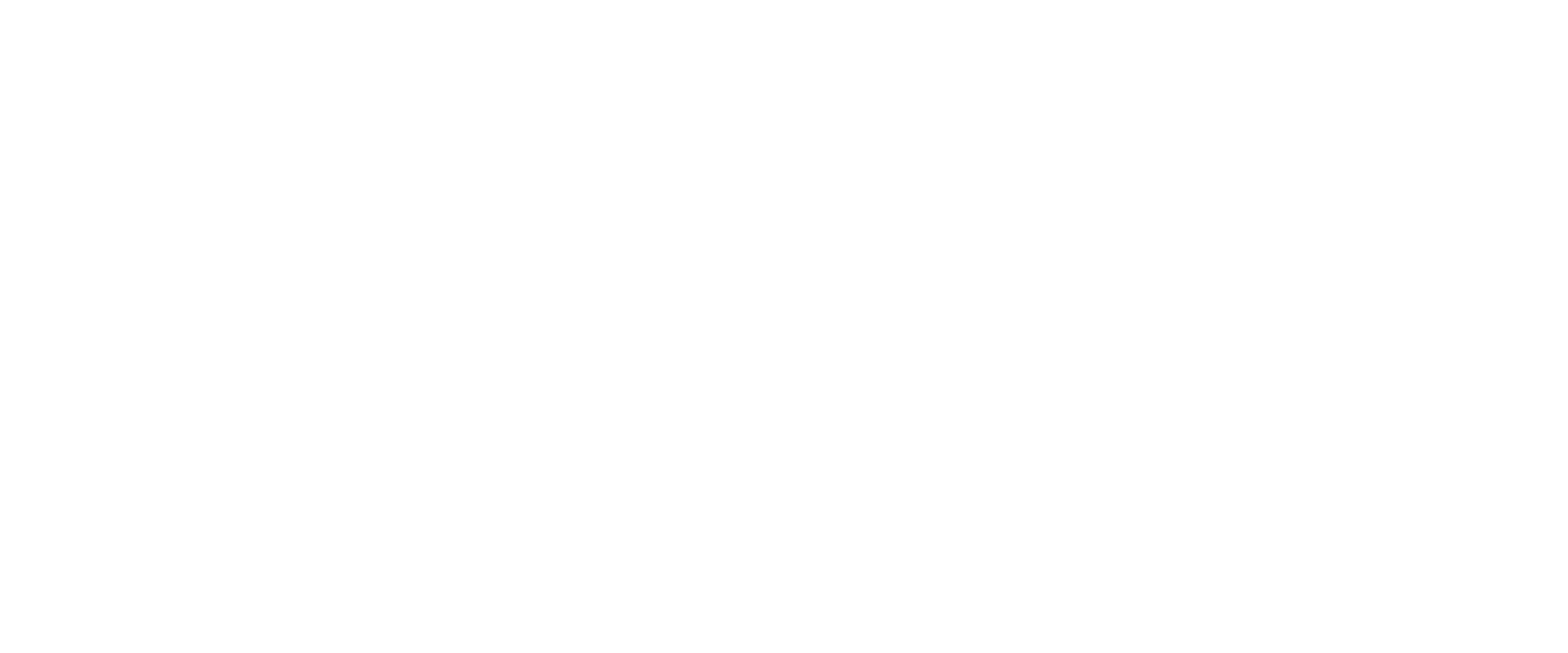
音鑑研究委員の先生による鑑賞授業 STEP UP!: 鑑賞指導のポイントや事例開発の視点について ~日本歌曲の事例をもとに~
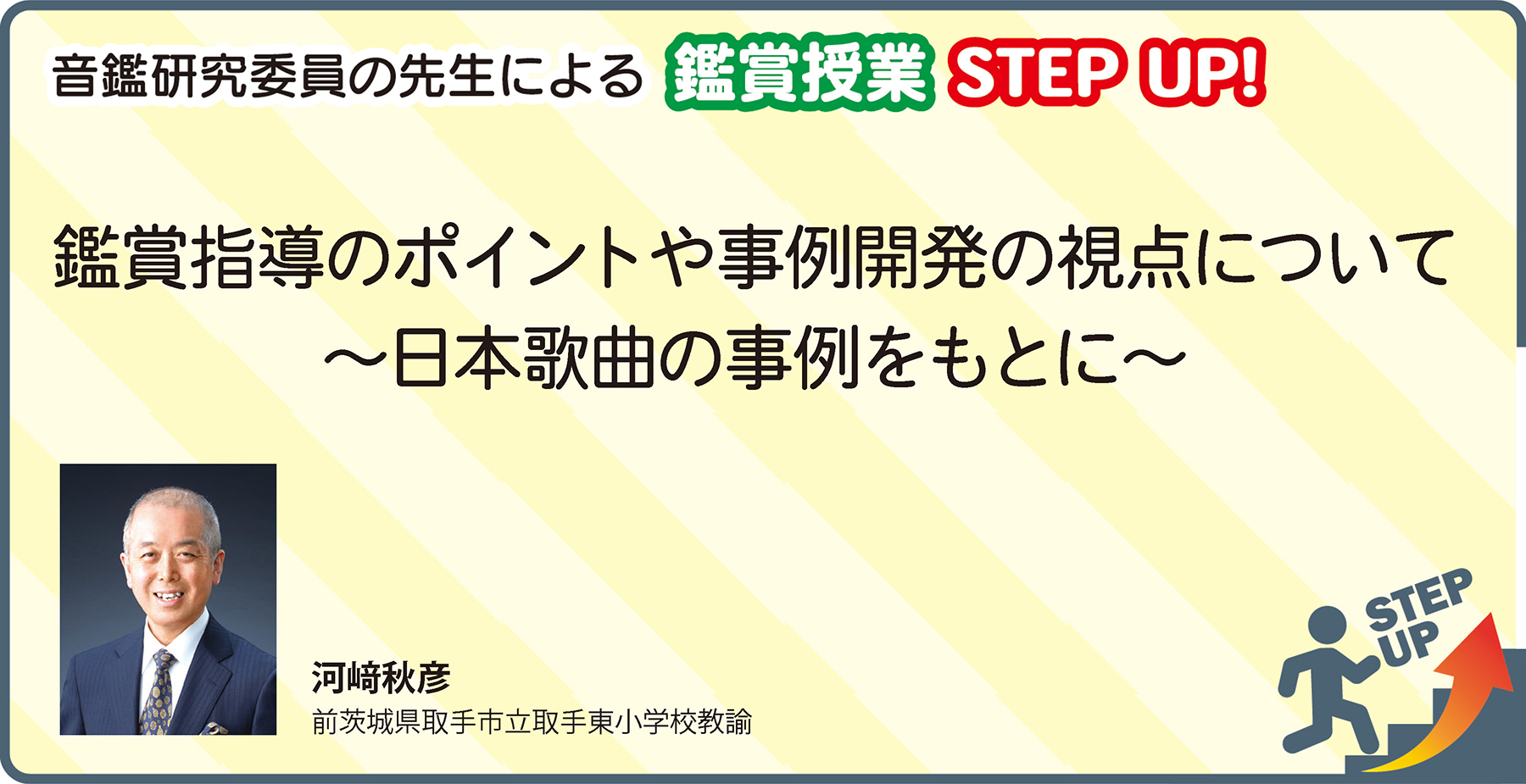
著者
河﨑 秋彦(前茨城県取手市立取手小学校教諭)
はじめに
音鑑では、研究委員会による指導事例と教材の開発を行っており、小中同一のテーマを設定し、定期的に意見交流をしながら運営している。本稿では、これまで研究委員会で大切にしてきた鑑賞指導のポイントや事例開発の視点の中から、①曲の魅力を探る、②教材音源の分析、③発問の工夫と体験的な学びについて、DVDブック事例集4「歌曲」(2019年8月発行)を例に紹介していきたい。
①曲の魅力を探る
──日本歌曲の特徴とは何か
音楽鑑賞の醍醐味は、曲を何度も聴き味わうことで、新たなよさや面白さを見い出していくところにあるのではないかと考える。
「歌曲」の鑑賞で印象に残る曲は何か、と問われて思い浮かぶ曲に、中学校の教材『魔王』(シューベルト作曲)を挙げる方は多いのではないか。『魔王』のように、ドイツ語の詩の内容と、詩の世界観を表す音楽とが一体となって表現されていくところが歌曲の大きな魅力のひとつである。日本歌曲も同様であり、詩の内容に伴う音楽表現を様々な演奏者で聴き比べ、その歌い方の違いのよさや面白さを発見できるような授業展開を目標に、教材化を図ることにした。
②教材音源の分析
──教師自身が音源の聴きどころを押さえて
音楽鑑賞指導で最も重要なことは、指導のねらいに最適な音源を教材にすることである。教師自身が音源をよく聴き、音楽を形づくっている要素を分析することが大切である。
小学校で学習する日本歌曲の多くは、旋律が同じでも1番、2番……で歌詞が異なる「有節形式」でつくられている(『魔王』のように、歌詞の意味や内容により旋律が異なるものは、「通作形式」と呼ばれている)。この「有節形式」は、旋律は全く同じでも、番号ごとに歌われる歌詞の内容の変化に伴い、歌い手の歌い方や、速度や強弱も変化していくところに面白さがある。また、同じ言葉が繰り返し続けて登場する場合は、その同じ言葉を歌い方の違い、速度や強弱の変化の違いで表現されることが多い。この言葉の繰り返しに着目し、4年生の児童に音楽的な変化が最も伝わると考えられる演奏の音源を、多くの音源の中から視聴して選び教材とした。
③発問の工夫と体験的な学び
──日本歌曲の指導例より
指導のねらいを児童が十分に把握し達成する上で大切なことは、教師の発問(発問の工夫)と、児童が聴く音楽を自分事として捉えられるような仕掛け(体験的な学び)である。
次に実際の指導の流れの中で、この2点を紹介していく。
〈実践〉小学校 第4学年
題材名
くり返しの表げんを感じ取ろう
教材
- 『めだかの学校』茶木滋作詞/中田喜直作曲
NHKのラジオ番組で発表された作品。茶木滋のオリジナルの詩の「そっとのぞいてみてごらん」の部分は1回のみの3行で構成されているが、中田喜直は、作曲の過程でこの部分の歌詞を同じ旋律で2回繰り返し、1回目はmp、2回目はppで歌うように指示している。 - 『ちいさい秋みつけた』サトウハチロー作詞/中田喜直作曲
サトウハチローは、中田喜直と組んで「新しいこどもの歌」の創作に意をそそいでいた。歌詞の「誰かさんが」と「ちいさい秋」の部分は、同じ言葉を3回続けて繰り返すという構造的な特徴がある。
題材の目標
- 速度や強弱などによる曲想の変化と、繰り返される歌詞の内容との関わりに気付いて聴く。
- 速度や強弱などによる曲想の変化、繰り返される歌詞の内容や歌唱表現についての知識を得たり生かしたりしながら演奏のよさや面白さを見いだし、日本の歌曲を味わって聴く。
- 演奏者が工夫する歌唱表現に親しみ、演奏を聴き比べたり友だちと意見を交流したりして繰り返しの表現を感じ取る学習に進んで取り組む。
取り扱う〔共通事項〕
(題材で主に取り扱うものを赤字表記)
本題材では、速度や強弱などによる曲想の変化と繰り返される歌詞(反復)の内容との関わりに気付くようにする。また、演奏者ごとの歌唱表現の工夫の違いを聴き取り、それぞれの歌唱表現のよさや面白さを感じ取りながら、日本の歌曲を味わって聴くようにする。
指導計画(全2時間)
(〇学習内容 ●主な学習活動)
【第1時】歌詞の繰り返しの部分の速度や強弱などによる曲想の変化を感じ取り、繰り返しの部分の歌唱表現のよさや面白さに気付いて聴く。
〇『めだかの学校』を聴き、歌詞の繰り返しの部分の強弱の変化を感じ取る。
👨『めだかの学校』の歌を、詩を見ながら歌ってみましょう。皆さんの知っている歌と、何か違いはありますか?
- 「そっとのぞいてみてごらん」のところが1回しかないです。
- いつもは、2行目のところを2回繰り返して歌っています。
●歌詞の繰り返しの部分の強弱の変化をワークシートに記入する。
●歌って確かめながら、歌詞の繰り返しの部分の強弱の変化を感じ取る。
課題意識をもつ導入の場面では「あれ?何だろう?」と意識する発問をすることが大切である。この場面では、作詞者のオリジナルの詩の通り「そっとのぞいてみてごらん」の部分を意図的に1回のみの歌詞を提示して歌い、その後、楽譜通りの2回目があることを発見することで、繰り返しの言葉の部分とその部分の強弱の変化を意識できるようにした。
〇『ちいさい秋みつけた』を聴き、速度や強弱などによる曲想の変化と、繰り返される歌詞の内容との関わりに気付く。
●ワークシートの歌詞の繰り返しの部分に線を引き、速度や強弱などによる曲想の変化を付けて音読し、歌唱表現の工夫の仕方を考える。
●ペアになり、「誰かさんが」や「ちいさい秋」の部分などを音読したり意見を交流したりしながら、歌唱表現の工夫について話し合う。
通常音楽を聴く行為は、受動的な活動になりがちであるが、ここでは、速度や強弱の変化をつけて音読する体験活動を取り入れた。この活動は、実際に歌うことが難しい日本歌曲であっても、いわば、歌を歌う疑似体験ができる活動である。この音読を取り入れることにより、この後に聴く演奏者の表現の工夫がどのようになっているのかを、関心をもって比べて聴こうとする姿勢に変容が見られた。
●『ちいさい秋みつけた』の全曲を聴き、速度や強弱などによる曲想の変化と繰り返される歌詞の内容などについてワークシートにまとめる。
【第2時】違う演奏者の『ちいさい秋みつけた』を聴き比べ、歌詞の繰り返しの部分の歌唱表現の工夫やそのよさを味わって聴く。
〇『ちいさい秋みつけた』の作詞・作曲者についてや、曲が作られた背景などについて知る。
●音源Aを全曲聴き、サトウハチローの家にあったハゼの木の写真や、中田喜直が曲の構想を練った公園にある歌碑を見て、作詞・作曲者が「ちいさい秋」を見つけた時の様子などを想像する。
👨作詞者のサトウハチローさんは、庭にあるハゼの木の赤くなった葉を見て秋の始まりを感じ、この詩を書いたそうです。また、作曲者の中田喜直さんは、秋の公園を散歩しているときに、この曲の旋律が浮かんだそうです。それでは、作詞・作曲者が見たハゼの木や、公園の様子を見てみましょう。

『ちいさい秋みつけた』では、作詞者がなぜ「ちいさい秋」と表現したのか、自由に想像し、秋の風景の一部であるハゼの木や公園の紅葉の様子を思い浮かべることで、音楽をより味わい深く聴くことができるようにした。サトウハチローの自宅にあったハゼの木が移植されている文京区・礫川公園と、中田喜直が曲の構想を練った記念の歌碑がある井の頭恩賜公園のそれぞれの紅葉の様子を、自ら写真に収め、資料とした。特にハゼの木の紅葉の特徴は、葉が1枚ずつ紅葉していく様子を感じ取ることができるように提示した。
〇歌詞の繰り返しの部分の速度や強弱などによる曲想の変化と歌唱表現の工夫を感じ取る。
●作曲者が楽譜に指示した強弱記号の意味をペアや全体で共有する。
●音源Aの1番を聴き、速度や強弱などによる曲想の変化と歌唱表現の工夫を感じ取り、繰り返しの部分の曲想の変化などについてワークシートにまとめ、発表し合う。
〇違う演奏者の音源を聴き比べ、それぞれの歌唱表現の工夫や、そのよさを味わう。
●自分の好きな演奏について、ワークシートに紹介文を書き、意見を交流する。
わたしのすきなえんそうは、Aの○○○○さんのえんそうです。Aをえらんだ理由は、3回くり返しているところの歌い方が一番好きだからです。それから、「よんでるくちぶえ」のところの歌の声が消えそうなところや、そのあとが、どんどんおそくなっていくところが心に残ったからです。みなさんも、ぜひきいてみてください。
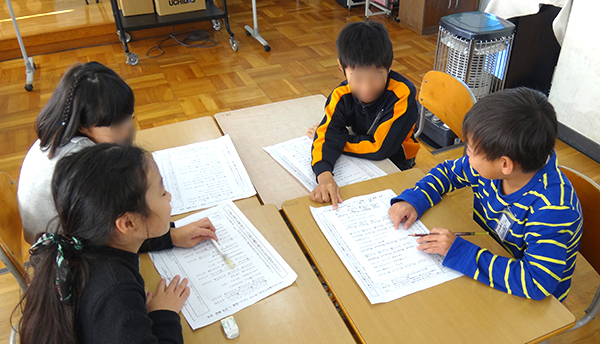
歌詞に速度や強弱の記号を書き加えたワークシートに歌い方を記入することで、歌詞の内容に焦点を当て、秋の風景を想像しながら聴くことができるようにした。また、第1時で音読による速度や強弱の変化をつけた音読の工夫をする体験的活動をすることで、第2時では曲の聴きどころを押さえ、具体的に紹介することができるようした。
おわりに
研究委員会では、「小中学校の連続的・発展的な学び」も大切な視点としてきた。中学校では、我が国の自然や四季の美しさを感じ取ることができる歌唱教材を扱うように示されている。小学校の段階としては、歌詞の内容とその世界を表す音楽から、日本の季節の移り変わりを思い浮かべながら、楽しんで音楽を鑑賞しようとする子どもを育てたいと考えている。
掲載号
季刊「音楽鑑賞教育」Vol.61(2025年4月号)